「考える力をつけたいけど、何から始めればいいんだろう?」
そんなふうに思ったこと、ありませんか?
難しい勉強や分厚い本じゃなくても大丈夫。
実は、日常にちょっとした工夫を加えるだけで、思考力ってグッと磨かれるんです
大事なのは“続けられること”。
1分でできること、毎日できること。
それを積み重ねるだけで、知的な習慣は自然と身につきます。
今回は、初心者でも今日からすぐ試せる「知的習慣の小技ベスト5」をご紹介します。
小技1:1分タイピング要約で考える力を強化

本や記事を読んだあと。
「いい話だったな〜」と思っても、数日後には忘れてしまう…。
そんな経験、ありませんか?
これは記憶力が悪いからじゃないんです。
人の脳は「インプットしただけ」だと、すぐに忘れるようにできているんですね。
そこでおすすめなのが、1分タイピング要約。
読んだらすぐ、パソコンやスマホで1分だけ打ち込む。
完璧な要約じゃなくてOK。
頭に浮かんだ言葉をそのまま打ち込むだけでいいんです。
たとえばビジネス書を読んだあとなら、
「大事なのは目的意識。手段に流されない」
この一行だけでも立派な要約。
心理学的にも効果があります。
有名なのが「エビングハウスの忘却曲線」。
人は時間とともに忘れるけれど、一度アウトプットするだけで記憶の定着率はグッと上がるんです。
私自身、この方法を試してから読書の理解度がまるで違いました。
以前は「あの本、どんな内容だったっけ…」と曖昧でしたが、今ではメモを見返すと頭の中がすぐに蘇ります。
しかも、自分の言葉でまとめてあるから読み返しやすい。
コツは「深く考えすぎない」こと。
たった1分。
“書くこと自体”に意味があるので、内容はざっくりで十分。
まずは今日読んだニュースでも構いません。
記事を読み終わったら、スマホで1分だけ打ち込んでみてください。
それだけで「知識が自分のものになった」という実感がわいてきますよ。

小技2:逆の立場で考える習慣で思考の幅を広げる
誰かの意見を聞いて「なんでそんな考え方するんだろう?」と思ったこと、ありませんか?
つい「自分の正しさ」だけで判断してしまう。
でもそれだと視野が狭くなってしまいます。
ここで試してほしいのが、1日1回、逆の立場で考えること。
会議で上司が下した決断。
ニュースで流れる政策。
家族の何気ない一言。
どんな場面でもOKです。
「もし自分がその人だったらどう考えるか?」
これを問いかけるだけ。
すると、意外な気づきが生まれます。
たとえば、上司の判断に「なんでそんな面倒なやり方を…」と思ったとき。
逆の立場で考えると、「組織全体を守るため」「部下を育てるため」などの背景が見えてきたりするんです。
心理学ではこれを「認知の柔軟性」と呼びます。
自分の立場を切り替える力。
これがある人は、問題解決がうまく、コミュニケーションもスムーズ。
ビジネスでも人間関係でも大きな武器になります。
私も実際にやってみて、イライラが減りました。
「なんでこんなこと言うの?」から「そういう見方もあるよな」へ。
たった1回立場を変えるだけで、気持ちが軽くなるんです。
ポイントは「正解を出そうとしない」こと。
ただ視点を変えてみるだけでいい。
毎日1回やれば、自然と「考えるクセ」が身についていきます。
今日からぜひ試してみてください。
世界の見え方がちょっと変わりますよ。
小技3:散歩中に“なぜ?”を3回で知的習慣トレーニング
ただ歩くだけの散歩。
リフレッシュにはいいけれど、頭はボーッとしがち。
でもここにちょっと工夫を加えると、散歩が“思考トレーニング”に変わります。
やり方はシンプル。
目に入ったものに「なぜ?」を3回繰り返すだけ。
たとえばコンビニの前に行列ができていたら…
「なぜ、並んでいるんだろう?」
「なぜ、この店だけ人気なんだろう?」
「なぜ、今この時間に集中するんだろう?」
最初は単純な疑問でも、繰り返すうちに原因や背景を考えるようになります。
「新商品の発売日だから」「立地条件がいいから」「人は行列を見ると安心するから」…
考える幅が一気に広がるんです。
この方法は、トヨタ式の「なぜを5回」の簡易版。
問題の根本に近づくための思考法として有名ですよね。
散歩に取り入れると、退屈な時間が一瞬で学びの時間に変わります。
私もよく試しています。
「なぜ、この公園のベンチはここにあるんだろう?」と考えたら、利用者の動線や日当たりのことまで想像が広がって面白いんです。
ただ歩いていたときには気づかなかった発見がどんどん出てきます。
ポイントは「答えを出すこと」よりも「問いを広げること」。
3回くり返すだけで、視野がグンと広がります。
ぜひ次の散歩でやってみてください。
日常の景色が、ちょっとした学びの教材に変わりますよ。

小技4:帰宅後に学びを声に出す習慣化のコツ
1日が終わって家に帰ると、ついダラっとしてしまう。
ニュースを見たり、スマホをいじったり。
気づけば「あれ、今日って何を学んだっけ?」なんて日もありますよね。
そこでおすすめなのが、帰宅後に“今日の学び”を声に出すこと。
たった一言でOK。
「今日は会議で質問力の大切さを学んだ」
「今日は時間を区切ると集中できると気づいた」
そんな感じで、一日の学びを一言でまとめます。
声に出すと何がいいか。
実は記憶に残りやすくなるんです。
心理学では「リハーサル効果」と呼ばれていて、声に出して繰り返すことで記憶が強化されるといわれています。
私も実際にやっています。
以前は「昨日何を学んだ?」と聞かれると答えに詰まることが多かったのですが、この習慣を始めてからはすぐに答えられるようになりました。
しかも声に出すと不思議と気持ちもスッキリします。
ポイントは完璧にまとめようとしないこと。
本当に一言でいいんです。
むしろ短い方が頭にスッと残ります。
誰かに伝えるつもりで声に出せば、説明力のトレーニングにもなります。
一石二鳥ですね。
帰宅後のほんの30秒。
この小さな習慣で、学びは記憶になり、そして知恵に変わっていきますよ。
小技5:毎朝“昨日の失敗”を1行書く小さな習慣
「昨日もあれがうまくいかなかったな…」
そんな反省って、心の中で終わらせていませんか?
そのままにすると、ただのモヤモヤで終わってしまいます。
そこでおすすめなのが、毎朝“昨日の失敗”を1行だけ書くこと。
ほんの一言でOKです。
「資料の準備が遅れた」
「会議で発言しそびれた」
「夜更かしして寝不足になった」
こんな感じで、サッと書き出すだけ。
これだけで頭が整理されます。
「失敗を認識する」→「次は気をつけよう」という流れが自然に生まれるからです。
心理学では、これを「セルフリフレクション(自己省察)」といいます。
振り返りを習慣化することで、失敗が“学びの資源”に変わるんですね。
私もやってみて感じたのは、「自己嫌悪」ではなく「次につながる小さな改善」ができるようになったこと。
昨日「夜更かし」と書いた日は、自然と今日は早く寝ようと思える。
積み重ねると、自分の成長がノートに残っていくのも嬉しいポイントです。
ポイントは深く分析しないこと。
ただ事実を一行にするだけ。
失敗を重く捉える必要はありません。
毎朝の1分で、昨日のつまずきを今日の知恵に。
失敗が“未来の自分を育てる材料”に変わりますよ。
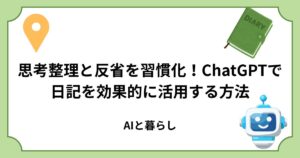
まとめ
知的習慣って、決してむずかしいものじゃありません。
分厚い本を読まなくても、勉強を詰め込まなくてもいい。
大事なのは、日常にちょっとした工夫を組み込むことなんです。
今回紹介したのは——
- 1分タイピング要約
- 逆の立場で考える
- 散歩中に「なぜ?」を3回
- 帰宅後に「今日の学び」を声に出す
- 毎朝「昨日の失敗」を1行書く
どれも1分、ほんのひと工夫でできる小技ばかり。
しかも続けることで、考える力がジワジワ育っていきます。
ポイントは「一度に全部やろう」としないこと。
気になったものをひとつだけ、今日から試してみる。
それが知的習慣の第一歩です。
小さな一歩が、気づけば大きな変化につながります。
あなたの毎日が、もっと知的で楽しい時間になりますように。
気になった小技をひとつだけ今日から試してみましょう!
他の習慣化アイデアはこちらの記事でも紹介していますので、ぜひ併せて読んでみてください。
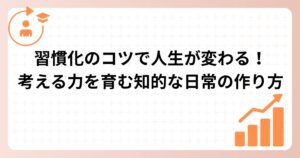


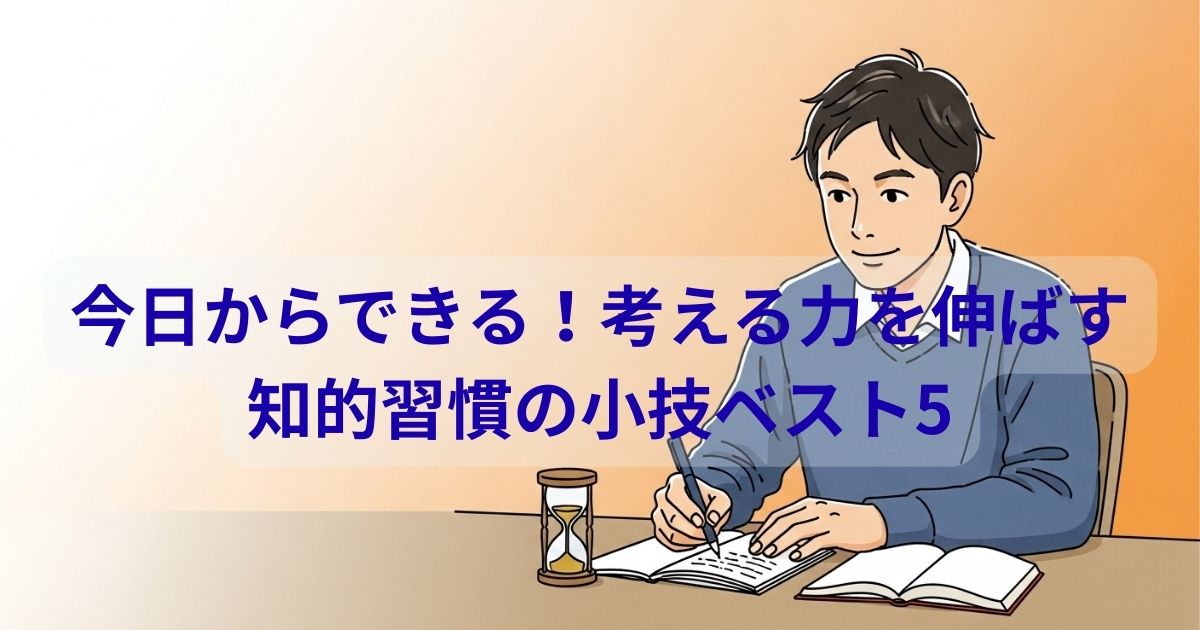
コメント
コメント一覧 (3件)
[…] あわせて読みたい 今日からできる!考える力を伸ばす知的習慣の小技ベスト5 「考える力をつけたいけど、何から始めればいいんだろう?」そんなふうに思ったこと、ありませんか […]
[…] メタ認知とは、自分の思考や感情を一歩… あわせて読みたい 今日からできる!考える力を伸ばす知的習慣の小技ベスト5 […]
[…] あわせて読みたい 今日からできる!考える力を伸ばす知的習慣の小技ベスト5 「考える力をつけたいけど、何から始めればいいんだろう?」そんなふうに思ったこと、ありませんか […]