「イシューから始めよ」は、“考える力”を鍛える人の必読書です。
どんなに努力しても、そもそもイシュー(本質の課題)がズレていれば成果は出ません。
私自身、BPRプロジェクトのリーダーとして、何度もこの「イシュー」を見極める場面に立ち会ってきました。
現場に足を運び、なぜを繰り返し、構造を見て、やっと見えてくる本質。
この本は、それを理論的に言語化してくれた一冊です。
今回は「イシューから始めよ」の内容に加えて、私の現場経験から得た“本質を見抜く思考法”を紹介します。
「イシュー」とは何か:問題ではなく“問い”から始める

成果を分けるのは「問いの質」
「イシューから始めよ」の最大のメッセージは、“正しい問いを立てることが成果を決める”という点です。
どれだけ分析しても、どれだけ努力しても、問いがズレていれば意味がない。
つまり「頑張りの方向」が大切なんです。
本書ではイシューを「解くべき本質的な問題」と定義していますが、ここで言う“問題”は「表面的な課題」ではなく、「この問いを解く価値があるか」という視点。
この一歩目を間違えると、どんなに優れたロジックも空回りしてしまいます。
「解けるかどうか」より「解く価値があるか」
多くの人がつい「解けるかどうか」に意識を向けがちですが、
本当に重要なのは「その問いを解く意味があるか」。
たとえば、日々の仕事の中で「売上を上げるにはどうすればいいか?」と考えるより、
「そもそもなぜ売上を上げる必要があるのか?」と問い直すほうが本質に近づけます。
この“問いの深さ”が、考える力の差になります。
イシュー思考は「仮説」から始まる
イシューを見極めるためには、最初に“仮説”を持つことが欠かせません。
仮説があることで、情報の取捨選択ができ、考える方向が定まります。
本書でも「最初に仮説を立てることが、効率的な思考の鍵」と説かれています。
これは、BPRの現場でもまったく同じ。
まず仮説を立てて現場を見に行き、「違う」と感じたら修正する——この繰り返しが、イシューを磨くプロセスそのものです。
では、実際に現場で“イシューを見極める”とはどういうことなのか?
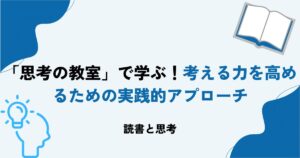
BPRの現場で学んだ「イシューの見極め方」
「イシューから始めよ」を読んで感じたのは、これは机上の理論ではなく、現場でこそ生きる考え方だということです。
私が長年、BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)のプロジェクトをリードしてきた中でも、最初にやるべきことは“イシューの特定”でした。
正しいイシューを見つけることができれば、あとの工程は自然に流れ始めます。
逆にここを誤ると、どれだけ優れた手法を使っても結果は出ません。
現地現物──現場に行かないと本質は見えない
私は必ず現場に足を運びます。
会議室ではなく、実際の作業フローや人の動きを見る。
そこには、データではわからない「違和感」や「無駄の構造」が隠れています。
現地で一次情報に触れることで、問題の“本当の姿”が見えてくる。
イシューは机の上ではなく、現場でしか見つかりません。
「なぜ?」を繰り返し、真因を掘り下げる
課題が見えたら、次に「なぜ?」を何度も繰り返します。
多くの人は1〜2回で止めてしまいますが、私は最低でも5回は掘ります。
たとえば「納期が遅れている」という表面的な問題があっても、
“なぜその仕組みになっているのか”“なぜその判断をしたのか”を掘り下げると、
本当のボトルネックが見えてきます。
この「なぜなぜ思考」は、まさにイシュー思考の現場版です。
構造として捉える──“点”ではなく“流れ”で見る
BPRでは、単一の問題よりも「構造的なつながり」に注目します。
たとえば、ミスが発生しているなら、その前後のプロセスの関係を見直す。
問題を“点”で捉えると対症療法に終わりますが、“流れ”で捉えると根本が見えます。
構造を描き出すと、「ここを変えれば全体が変わる」というレバレッジポイントが浮かび上がります。
外を見る──異業種・世の中の動向から学ぶ
イシューを見極めるには、社内だけを見ていては限界があります。
異業種の成功事例や、世の中の変化を調べることで、
「自分たちは何を変えるべきか」という視点が研ぎ澄まされます。
特にBPRのように大きな変革を伴う仕事では、既存の枠を超える視野が不可欠です。
未来を描く──「あるべき姿」ではなく「ありたい姿」へ
そして最後に、私はいつも「あるべき姿」ではなく「ありたい姿」を描きます。
理想を押しつけるのではなく、「自分たちはどうありたいか」を対話の中で見つける。
そこに組織の意志が宿ります。
イシューとは、“正解を探す”ことではなく、“共感を生む問いを立てる”こと。
この視点があると、改革は人を動かす力を持ちます。
イシューを見極めるとは、現場を観察し、構造を理解し、未来をデザインすること。
次の章では、この「イシュー思考」をどうやって日常の思考法として磨いていけるかを考えていきます。

イシューを見つける“問いの立て方”

イシューを見極めるには、「良い問い」を立てる力が欠かせません。
問いが浅ければ、思考も浅くなる。
逆に、問いが深ければ、自然と見えてくる景色も変わります。
「イシューから始めよ」は、その“問いの設計図”を教えてくれる本でもあります。
ここでは、私自身が現場で実践してきた「問いを立てる」ための3つのステップを紹介します。
「ありたい姿」を描く──ビジョンが問いを導く
多くの人は「あるべき姿」から考えようとしますが、
私はあえて「ありたい姿」からスタートします。
“こうあるべき”は過去の延長線上にありますが、
“こうありたい”は未来をデザインする思考です。
BPRでもブランド企画でも、最初に描くのは「理想像」ではなく「願望に近い未来」。
「自分たちはどういう存在でありたいのか」という問いを立てると、
自然と「では、何を変えるべきか?」というイシューが浮かび上がります。
問いは、未来への意志から生まれるのです。
「構造をどう変えるか」を考える──問題を“動かす視点”を持つ
イシューを考えるとき、私は「何を変えるか」より「構造をどう変えるか」に注目します。
たとえば、売上や業務効率という“結果”を追うのではなく、
その結果を生み出している“仕組み”や“人の動き”に目を向ける。
構造を変える発想を持つことで、問題の本質が浮かび上がります。
これは、「解決」ではなく「再設計」の思考。
本書でも「イシューは構造の理解から生まれる」と述べられていますが、
まさに現場で感じる実感と一致します。
「なぜ今、それが重要なのか」を問う──時間軸で価値を測る
良い問いには、必ず“タイミングの意識”があります。
どんなに立派なテーマでも、今取り組む意味がなければ人も動かない。
私は常に、「なぜ今なのか?」を自分に問いかけます。
この視点を持つと、イシューは抽象論から具体的な行動へと変わります。
たとえば「DXを進める」ではなく、「今の組織文化のままでDXは本当に実現できるのか?」と問う。
このように、時間と構造を交差させた問いが、思考の深さを生みます。
問いを“仮説”として持ち歩く
イシューを見つけるための問いは、最初から完璧である必要はありません。
むしろ、仮説として動かしながら磨いていくもの。
現場を見て、他者と話し、情報を集めるたびに問いを更新していく。
それが、思考を進化させるプロセスです。
私はいつもノートに「いま考えている問い」を書き留め、
週に一度は見返して“今も意味があるか”を確認しています。
イシューとは、時間とともに育っていく“生きた問い”なのです。
良い問いは、正解を導くためではなく、新しい視点を生むためにある。
イシュー思考の本質は、答えを出すことではなく、「問いを育て続けること」。
次の章では、その問いを“行動”につなげるためのテクノロジー活用と実践法を紹介します。

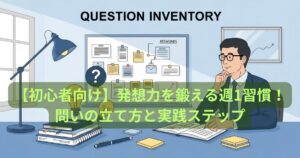
解決の道を開くために:デジタルテクノロジーで“イシューを磨く”
私がBPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)のプロジェクトを進めていた頃、AIはまだ存在していませんでした。
それでも、デジタルテクノロジーはすでに“思考を磨くための道具”として力を発揮していました。
システム導入やツールの選定は目的ではなく、あくまで 「イシューを明確にし、構造を見える化するための手段」。
DXを推進する中で私が実感したのは、デジタルの本質は「解決の自動化」ではなく、「考えるプロセスの可視化」だということです。
デジタルは「効率化の道具」ではなく「構造を見える化する道具」
BPRの現場で最も重要だったのは、“見えない構造”をどう可視化するかでした。
現場のヒアリングやデータ分析を経て、業務フローをデジタルツール上で整理し、
ボトルネックや手戻りがどこに潜んでいるかを浮かび上がらせる。
それを全員が同じ画面で共有することで、課題の認識が一致し、議論の質が一気に上がります。
デジタルは「業務を早くするツール」ではなく、「思考を構造化するためのレンズ」。
目に見えない因果関係を描き出すことで、イシューの輪郭がはっきりしていくのです。
仮説検証を“デジタルで高速化”する
イシューを磨く過程では、「この新しいプロセスは本当に効果があるのか?」を
いかに早く確かめるかが鍵になります。
以前は、業務フローを紙に描き、会議で議論し、試行するまでに数週間かかっていました。
しかし今は、デジタルテクノロジーを活用すれば、仮説の立案から検証までを圧倒的に短縮できます。
私がDXを推進していたときも、最初から完璧な仕組みを作るのではなく、
まずは 「新しいプロセスに必要な最低限のツールを活用し、実際に効果があるかを検証する」 ことから始めていました。
たとえば、既存の業務管理ツールやファイル共有システムを組み合わせ、
最小限のチームで試験運用してみる。
数日後には成果データを見ながら改善点を洗い出し、すぐに次の仮説を立てる。
この“スモールスタートで高速検証”のサイクルを回すことで、
理論上のアイデアが実際に現場で機能するかを素早く確認できます。
デジタルの強みは、試行錯誤のスピードと修正の柔軟性。
失敗のコストが小さいからこそ、考える手を止めずにイシューを磨き続けられるのです。
「解決」よりも「再設計」を目指す
デジタル導入のゴールは「問題を解決すること」ではなく、「構造を再設計すること」にあります。
新しいツールを入れても、旧来の考え方のままでは結果は変わりません。
だからこそ、まず「どの構造を変えるべきか」というイシューを明確にすることが最優先。
私は常に、テクノロジーを “仕組みを描き直すための思考ツール” として使ってきました。
その結果、現場の理解が深まり、組織全体が「自分たちで構造を変える」という意識を持ち始めたのです。
デジタルが“問い”を磨く
DXを進めて感じたのは、デジタルテクノロジーは答えを出すための装置ではなく、
「問いを磨く装置」 だということです。
新しいデータが見えるようになると、これまで当然だと思っていた前提が揺さぶられます。
「そもそも何を目的にしていたのか?」
「この仕組みは本当にお客様に価値を届けているのか?」
──そんな根本的な問いが次々に浮かび上がるのです。
テクノロジーは、思考を止めるものではなく、思考を深めるための“触媒”。
人とデジタルが対話を重ねながら問いを磨いていく。
それが、イシュー思考を進化させるDX時代の知的プロセスなのです。
デジタルテクノロジーは、効率化のための仕組みではなく、
「考える力」を加速させる知的なインフラです。
イシューを磨くとは、デジタルの力で思考の構造を見える化し、
小さく試して、何度でも描き直すこと。
それこそが、私がBPRとDXを通じて学んだ「知的な問題解決の本質」でした。

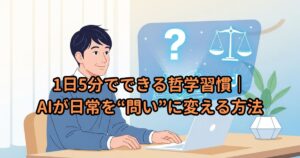
考える力を育てる習慣:AI時代の“イシュー思考”を日常に

イシュー思考は、特別なプロジェクトや会議のためのスキルではありません。
むしろ、日常の中で「なぜ?」「本質は?」と問い続けることで鍛えられる“思考の習慣”です。
そして今は、AIという強力なパートナーが加わりました。
AIを使えば、誰でも自分の思考を客観的に見つめ、イシューを磨くトレーニングができます。
まさに、BPRやDXの現場で行っていた「構造を見て、仮説を立て、検証する」プロセスを、
個人レベルでも実践できる時代になったのです。
ニュースを“構造”で読む──AIが思考の補助線を引く
ニュースを読むときも、ただ情報を受け取るだけではなく、
「なぜ今この出来事が起きているのか」「背景にある構造は何か」を考えてみる。
AIを使えば、記事を要約するだけでなく、因果関係や関連データまで瞬時に提示してくれます。
それを見ながら、「この視点は正しいか?」「別の要因はないか?」と問い直すことで、
思考はより立体的になります。
AIは答えを与える存在ではなく、“考えるための補助線”を引いてくれる存在です。
「なぜ?」を3回繰り返す──AIに問い返してもらう
イシュー思考の基本は「なぜ?」を繰り返すこと。
たとえば、「仕事が忙しい」と感じたら、
「なぜ忙しいのか?」「なぜその仕事を自分がしているのか?」「なぜ今やる必要があるのか?」
と深掘りしていく。
AIにその問いを投げかけると、論理の矛盾や見落としを指摘してくれます。
これはまるで、自分の中に“もう一人の思考パートナー”がいるような感覚です。
問いをAIに見せることで、自分の思考の浅さや偏りが浮き彫りになる。
この習慣を続けるだけで、考える力が驚くほど鍛えられます。
ノートとAIで“思考の履歴”を残す
私は今でもノートに「今日の問い」を書き留めています。
手書きのノートには“考えの温度”が残るからです。
ただ、AI時代の思考術としては、それをデジタルに残す工夫も効果的です。
AIノートアプリやクラウドメモを使えば、
自分の問いや仮説を時系列で整理し、AIが自動的にタグづけや要約をしてくれる。
過去の自分がどんな問いを持っていたか、どんな答えにたどり着いたかが一目でわかります。
これは、まさに“思考の資産化”です。
AIと“思考の対話”を習慣化する
AIを使う上で大切なのは、「答えをもらう」より「問いを深める」こと。
たとえば、AIに「この企画の弱点は?」「他の視点から見たら?」と投げかけてみる。
すると、自分では気づかなかった切り口や矛盾点が返ってきます。
AIとの対話は、思考を広げ、仮説を磨くためのリフレクション(内省)の時間になります。
これは、かつてBPRの現場でチームメンバーと議論を重ねていたのと同じ構造です。
今はそれを、AIという知的なパートナーと一対一で行えるのです。
イシュー思考の本質は、「良い答えを出す」ことではなく、「良い問いを持ち続ける」こと。
AIやデジタルテクノロジーは、その問いを映し出し、磨き続ける鏡のような存在です。
毎日の中で小さなイシューを見つけ、それをAIと共に考え続ける。
それこそが、これからの時代における“知的生活”の核心なのです。
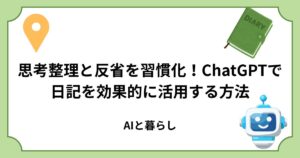

まとめ:すべての思考は“イシュー”から始まる
「イシューから始めよ」は、成果を出すための思考術でありながら、
実は“自分の頭で考えて生きる”ことの大切さを教えてくれる本です。
本質を見抜くとは、正解を探すことではなく、
「自分は何を大切にし、何を変えたいのか」を問い続けること。
私はBPRやDXの現場で、その問いと何度も向き合ってきました。
構造を描き直し、人を動かし、時には失敗を繰り返しながら見えてきたのは、
“イシューを見極める力”こそが、すべての成果を左右するということです。
いま、私たちはAIという新しい知的ツールを手にしています。
AIは答えを出してくれる存在ではなく、問いを磨き直すためのパートナーです。
AIと対話しながら、自分の考えを見つめ直す。
それはまさに、かつて現場で仮説を立て、検証を繰り返してきたあのプロセスの個人版。
イシュー思考は、時代を超えて「考える力の原点」なのです。
そして最後に──
あなたにとって、今いちばん解くべき“イシュー”は何ですか?
それを見つけることが、知的な日常を生きる第一歩になるはずです。
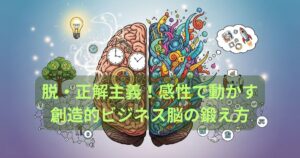
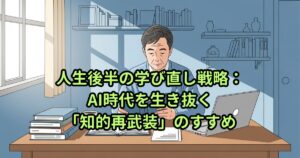
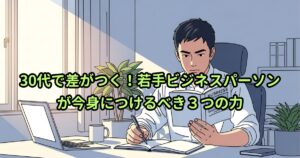

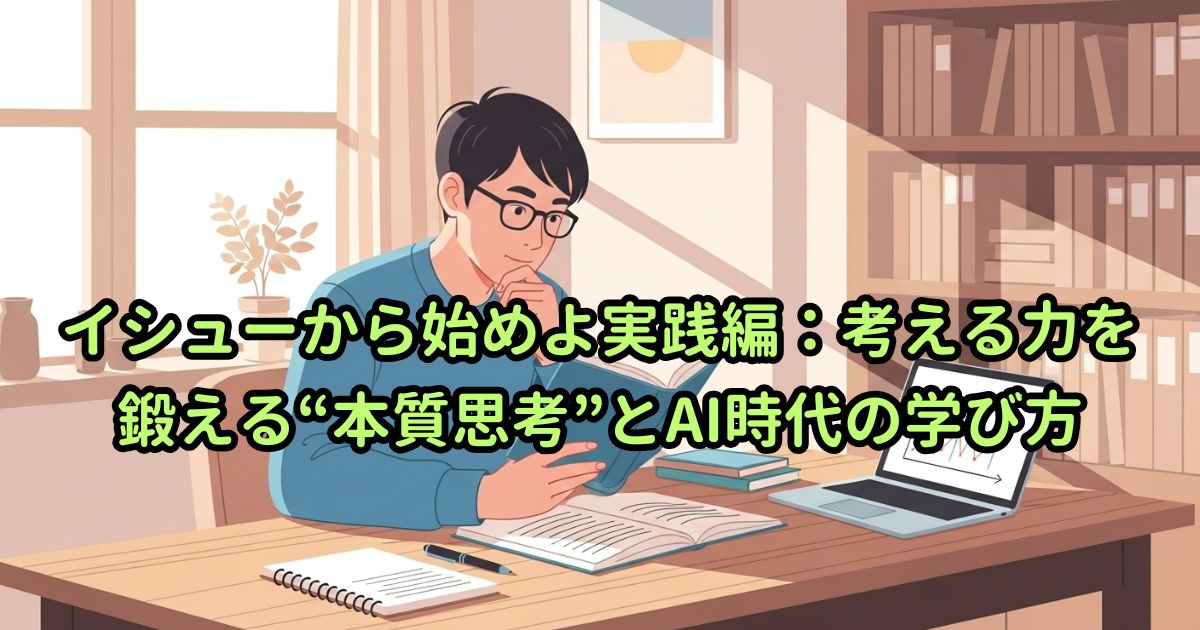
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] あわせて読みたい イシューから始めよ実践編:考える力を鍛える“本質思考”とAI時代の学び方 「イシューから始めよ」は、“考える力”を鍛える人の必読書です。どんなに努力し […]