気づいたら、もう30代が見えてきた。
なんとなく働いてきたけれど、このままでいいのかな——。
そんな不安、ありませんか?
『ビジネスパーソンに必要な3つの力』(山本哲郎著)は、
「今のうちに身につけておくべき力が何か」を教えてくれる本です。
それは、自己基盤力・課題解決力・論理的コミュニケーション力。
どれも一見あたり前。でも、できている人は意外と少ない。
20代の今、この3つを意識して磨いておくかどうか。
それが、30代後半からのキャリアに“大きな差”を生む。
焦る必要はありません。
むしろ「今だからこそ、始められる」。
今日から一歩、未来の自分を育てていきましょう。
若手ビジネスパーソンに「3つの力」がなぜ必要なのか

20代の今こそ「差がつく準備期間」
20代は、がむしゃらに仕事を覚える時期。
言われたことをこなすだけでも精一杯ですよね。
でも、気づかないうちに周りとの“差”は生まれています。
その差を生むのが、この「3つの力」。
30代になってから頑張っても、基礎ができていないと伸びにくい。
だからこそ今、成長の「型」を身につけておくことが大切です。
自己基盤力で「ぶれない自分」をつくり、
課題解決力で「考える力」を鍛え、
論理的コミュニケーション力で「伝える力」を磨く。
この3つがあれば、どんな環境でも成長できる。
それが著者・山本哲郎さんのメッセージです。
「頑張っているのに評価されない」原因
「仕事、ちゃんとやってるのに…」
そう感じたこと、ありませんか?
実はそれ、能力が足りないわけではないんです。
原因は、“考え方と伝え方”のズレ。
たとえば、がむしゃらに頑張っても方向がズレていたら成果につながらない。
あるいは、良いアイデアを持っていても上手く伝えられない。
つまり、仕事の成果は「自分をどう立て直し」「どう考え」「どう伝えるか」で決まる。
この3つの力は、そのすべてを支える“仕事のエンジン”なんです。
30代からのキャリアは「20代の土台」で決まる
30代になると、リーダーシップを求められたり、後輩ができたり。
「人を動かす力」が必要になります。
でも、そのときに支えるのは技術ではなく“人間力”。
ぶれない軸を持ち、課題を整理し、論理的に話せる人が信頼される。
だからこそ、20代のうちに「3つの力」を磨いておく。
それが、未来のキャリアをスムーズに進める最大の投資です。
自己基盤力:迷わず行動できる「心の軸」をつくる
自分を信じる“土台”を持とう
仕事で悩んだとき、つい周りと比べて落ち込むこと、ありませんか?
「あの人は結果を出してるのに、なぜ自分は…」って。
でも、そこで必要なのが「自己基盤力」。
これは、スキルでも知識でもなく、自分を支える内面の強さです。
たとえば、うまくいかなくても「自分なら大丈夫」と思える心。
他人の評価に揺れずに、自分の価値を自分で認められる力。
つまり、自己承認力=自己基盤力のコアなんです。
他人に承認されなくても、自分で「今日もよくやった」と言えるかどうか。
それが、成長のエネルギーになります。
自己否定グセをやめると、行動が変わる
多くの人がつまずくのは、「自分責めのクセ」。
失敗すると、「なんで自分はダメなんだ」と思ってしまう。
でも、自己基盤力を持つ人は違います。
失敗を“成長の材料”として受け止めるんです。
「できなかった」ではなく「次はどうする?」に切り替える。
この一歩の違いが、未来の結果を変えます。
小さな成功を見つけて、自分を褒める。
「昨日より少し前進した自分」をちゃんと認める。
それが自己承認のトレーニングです。
心の軸を鍛える3つの習慣
では、どうすれば自己基盤力を育てられるのか?
ポイントは、**日々の小さな“内省の習慣”**です。
- 日記をつける — 感情を「書いて整理」する。
- 読書をする — 他人の思考を借りて、自分の軸を見つめ直す。
- 静かな時間を持つ — 5分でも「何も考えない」時間をとる。
この3つを続けるだけで、心の揺れが少なくなります。
他人に振り回されず、自分のリズムで動けるようになる。
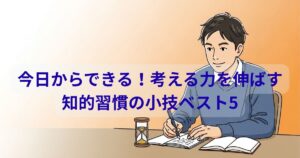
自分を肯定できる人は、他人も支えられる
最終的に、自己基盤力がある人は「人に優しく」なれます。
なぜなら、自分を認められる人は、他人の違いも受け入れられるから。
自分にOKを出せる人は、挑戦を恐れず、行動が速い。
そして、そんな人の周りには自然と信頼が集まります。
だからこそ、まずは自分を認めることから始めよう。
「今日もよくやった、私」。
そのひと言が、未来の自分を育てる一番のエールです。
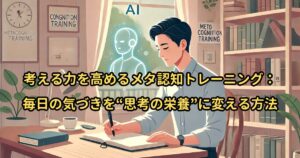
課題解決力:問題を「構造」で捉える力
がむしゃらよりも「考える力」
仕事を頑張っているのに成果が出ない——。
そんなとき、もしかしたら“やり方”ではなく“考え方”がズレているのかもしれません。
課題解決力とは、「とにかく動く」力ではなく、本質を見抜く力のこと。
表面の問題に飛びつかず、根っこを掘り下げる。
この思考の深さが、結果の差をつくります。
「Why → How → What」で考える
課題を整理するときに使えるのが、Why・How・Whatのフレームです。
- Why(なぜ):そもそも、なぜこの課題に取り組むのか?
- How(どうやって):どんな方法で解決できるか?
- What(何をするか):具体的に何を実行するか?
多くの人は、いきなり「What」から入ります。
つまり、「何をやるか」だけに意識がいってしまう。
でも、最も重要なのはWhy(なぜ)。
なぜそれをやるのか。
なぜ今なのか。
なぜその方法なのか。
この「Why」が明確になると、行動にブレがなくなります。
逆にWhyをすっ飛ばすと、頑張ってもズレた努力になる。
成果が出ない人は、ここでつまずいていることが多いんです。
「なぜ?」を3回繰り返すだけで深くなる
たとえば、上司から「報告が遅い」と指摘されたとします。
「早く出そう」と思うだけでは、表面対応です。
そこで「なぜ遅れているのか?」を3回繰り返してみましょう。
- なぜ遅れている? → 他の作業が多いから
- なぜ多い? → 優先順位が整理できていないから
- なぜ整理できていない? → タスクの見える化をしていないから
こうして掘り下げると、「根本原因=タスク管理の問題」だとわかる。
課題解決とは、“症状”ではなく“構造”を見ることなんです。
考える力を鍛える3つの習慣
- 書き出す習慣 — 頭の中だけで考えない。
- 問いを立てる — まず「なぜ?」から始める。
- 人に説明する — 話すことで論理が磨かれる。
この3つを繰り返すうちに、自然と「考える癖」が身につきます。
思考が整理され、行動の優先順位もクリアになる。

「Why」で生きる人は、ぶれない
結局のところ、課題解決力とは“目的意識”の強さです。
Whyを持っている人は、どんな仕事にも意味を見出せる。
そして、その意味が行動を後押ししてくれます。
表面的な正解よりも、「なぜ自分はこれをやるのか」。
この問いを持ち続ける人こそ、未来を切り拓ける人です。
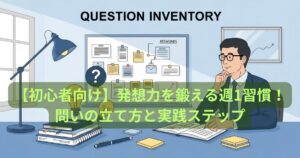

論理的コミュニケーション力:伝わる人が伸びる理由
「伝えている」と「伝わっている」は違う
「ちゃんと説明したのに、伝わってない…」
そんな経験、ありませんか?
多くの人は「話した=伝えた」と思っています。
でも、相手に理解されて初めて“伝わった”ことになる。
論理的コミュニケーション力とは、
ただ話す力ではなく、相手の頭の中を整理してあげる力なんです。
「結論→理由→具体例」で伝える
シンプルだけど最強なのが、PREP法。
- Point(結論):最初に結論を言う
- Reason(理由):なぜそう思うのかを説明
- Example(具体例):実例でわかりやすく
- Point(再結論):最後にもう一度まとめる
たとえば会議で意見を言うとき。
「私はA案に賛成です(結論)。なぜなら〜(理由)…」
この流れにするだけで、聞き手の理解度は格段に上がります。
「How」より「Why」を意識すると説得力が増す
多くの人は「どうやって伝えるか(How)」ばかり考えがち。
でも、本当に相手の心を動かすのは「なぜそれを伝えるのか(Why)」です。
「なぜ伝えたいのか」
「なぜ相手に知ってほしいのか」
この“想いの根っこ”が明確だと、言葉に温度が生まれます。
ロジックだけではなく、Whyがあることでメッセージに深みが出る。
だからこそ、「何を言うか」より「なぜ言うか」を大切にしたい。
聞く力も、立派な論理的スキル
論理的コミュニケーションというと、「話す」イメージが強いですよね。
でも、実は聞く力こそがベースです。
相手の話を途中でさえぎらず、まずは最後まで聞く。
言葉の裏にある「意図」や「感情」をくみ取る。
この姿勢があるだけで、相手は安心して心を開きます。
そして、相手の話を整理して返す。
「つまりこういうことですね?」
この一言で、会話は一気に“伝わる”方向に進みます。
伝わる人は、チームを動かす人
どんなにスキルが高くても、
伝わらなければ評価されません。
逆に、論理的に・思いやりをもって伝えられる人は、
チームをまとめ、信頼を得て、結果を出す人です。
だからこそ、「伝える力」はキャリアの加速装置。
今からでも遅くない。
言葉の使い方を少し意識するだけで、仕事の景色が変わります。
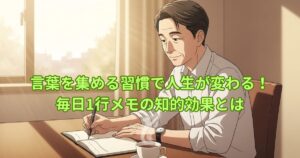
3つの力を同時に伸ばす「知的生活」のすすめ
3つの力は、バラバラじゃない
ここまで紹介してきた3つの力。
自己基盤力・課題解決力・論理的コミュニケーション力。
実はこの3つ、別々に鍛えるものではありません。
ひとつが伸びると、自然に他の力もつながっていくんです。
たとえば、自己基盤力で「ぶれない軸」ができると、
課題解決でも迷わなくなる。
そして、考えが整理されるから、伝える力も磨かれる。
つまりこの3つは、知的生活の“三本柱”。
毎日の過ごし方を少し変えるだけで、
自然と3つの力がバランスよく育っていきます。
本を読む・書く・話すをセットで回す
最もおすすめの鍛え方は、「読む・書く・話す」の3ステップ。
- 読む(インプット):知識を広げ、考えの材料を増やす。
- 書く(アウトプット):頭の中を整理し、自分の意見を形にする。
- 話す(コミュニケーション):相手の反応から、伝え方を磨く。
このサイクルを日常に取り入れると、
考える力も伝える力も同時に伸びていきます。
たとえば、読んだ本の気づきをメモして、友人に話す。
それだけでも、知的筋トレになります。
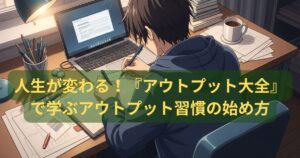
AI時代こそ「考える力」が差を生む
AIが進化する時代だからこそ、
人間が磨くべきは「思考」と「表現」の力です。
AIは情報を整理するのは得意。
でも、「なぜそれをするのか(Why)」を決めるのは人間。
つまり、3つの力を鍛えることは、
AI時代に通用する人間力を育てることなんです。
AIを使いこなす人は、結局「考える人」。
思考力・発想力・共感力をもって、未来をデザインしていく人です。

「知的生活ラボ」流・小さな始め方
いきなり全部やろうとしなくてOK。
大切なのは、「小さく始めて続けること」。
たとえば、
- 朝5分の読書をする
- 仕事の振り返りを1行書く
- 会議でひとこと意見を言う
これだけでも、3つの力は少しずつ育っていきます。
積み重ねが“自信の土台”になる。
今日の小さな行動が、
明日の「考える力」につながる。
さあ、あなたも今日から一歩、
“知的生活”を始めてみませんか?
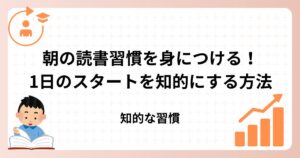
まとめ:未来のあなたは、今日の一歩で変わる
自己基盤力で「自分を信じる心」を育て、
課題解決力で「考える筋肉」を鍛え、
論理的コミュニケーション力で「伝える力」を磨く。
この3つの力は、どれも一朝一夕では身につきません。
でも、今日の一歩から始まります。
焦らなくていい。
比べなくていい。
昨日の自分より、少しだけ前へ。
その積み重ねが、未来のあなたをつくります。
“考えることを習慣にする”
それが、知的生活の第一歩。
小さな知的行動を、今日から一緒に始めましょう。
私からひとこと
実は、私自身もこの本を読んで改めて感じました。
「若い頃、この3つの力を意識して磨いてきたから、今の自分がある」と。
私は大企業でBPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)プロジェクトのリーダーとして、
数多くのプロジェクトを動かしてきました。
その経験の土台になっていたのが、まさに——
自己基盤力・課題解決力・論理的コミュニケーション力です。
だからこそ、今の20代・30代前半の方に伝えたい。
この本、『ビジネスパーソンに必要な3つの力』(山本哲郎著)は、
間違いなくあなたの“キャリアの原点”になる一冊です。
ぜひ、読んでみてください。
きっと、未来の自分へのヒントが見つかります。



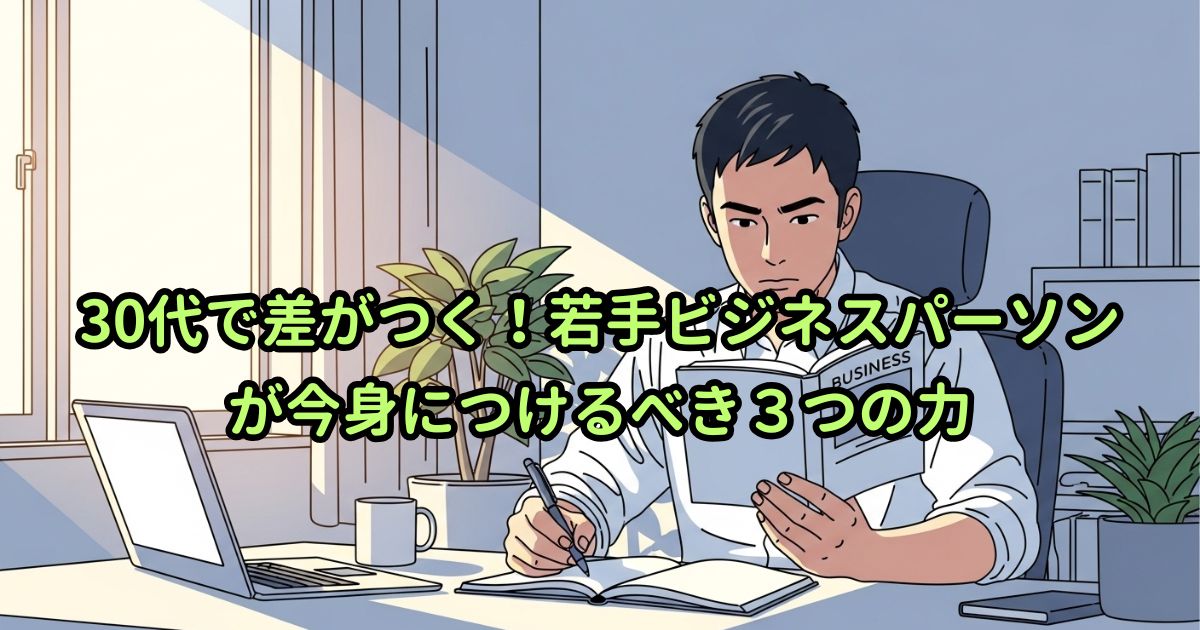
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] あわせて読みたい 30代で差がつく!若手ビジネスパーソンが今身につけるべき3つの力 気づいたら、もう30代が見えてきた。なんとなく働いてきたけれど、このままでいいのかな— […]