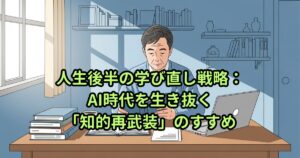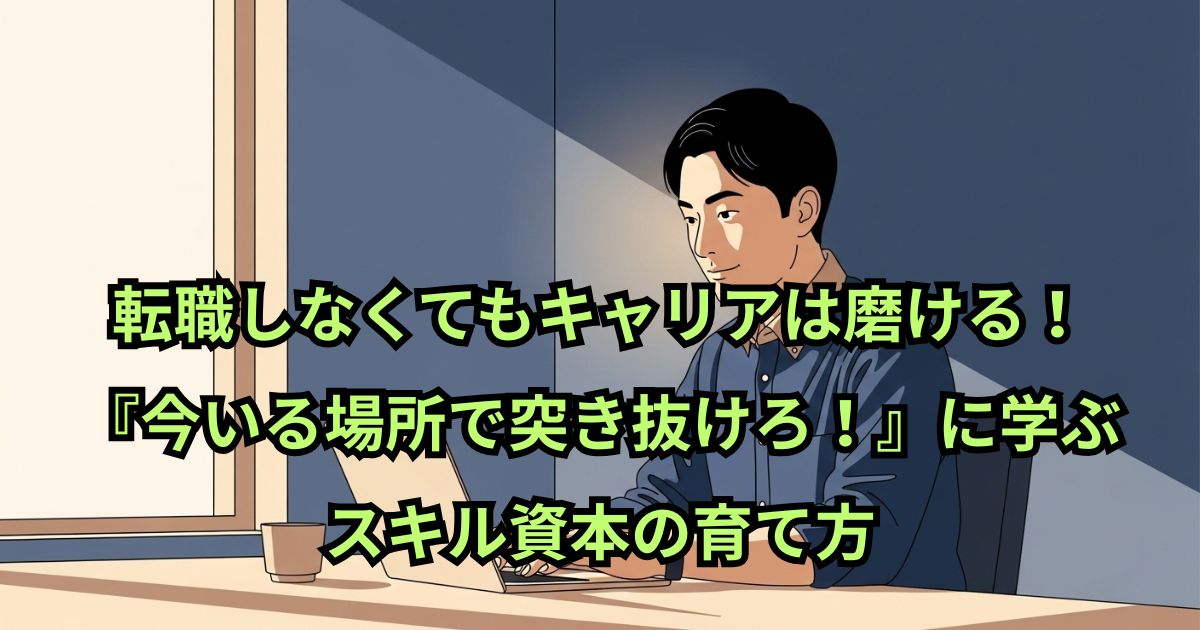仕事がマンネリ化してきたとき、つい「そろそろ転職かな」と思ってしまうこと、ありますよね。
でも、カル・ニューポートの『今いる場所で突き抜けろ!』を読むと、少し考え方が変わります。
私自身、長く同じ会社にいながらも、まったく文化の異なる3つの部門を経験してきました。
最初は戸惑いの連続。
でも、どんな環境でも“やりきる”と、面白くなってくるんです。
そこで突き抜けた存在になると、相談が舞い込み、ネットワークが広がり、良い循環が生まれる。
今回は、この本と私の実体験から「今いる場所でキャリアを磨く」ためのヒントをお伝えします。
転職がすべてじゃない。「今いる場所」で成長する視点

「転職すれば変われる」と思っていたけれど
転職サイトを開けば、魅力的な求人が並んでいます。
「もっと自分に合う仕事があるかも」と思うのは自然なこと。
でも、少し立ち止まって考えてみたいんです。
「今の場所」で、もう一段上に行ける余地はないだろうか?
実は、職場を変えなくても成長できる方法はたくさんあります。
ポイントは、“自分のスキルをどう育てるか”という視点なんです。
異なる文化に飛び込むと、世界が広がる
私自身、長く同じ会社にいながらも、
まったく文化の違う3つの部門を経験してきました。
最初は戸惑いだらけ。言葉もルールも、人の動きも違う。
でも、不思議なもので、やっていくうちにだんだん面白くなってくるんです。
「これって、あの部署のやり方より効率的かも」
「この仕組み、他のチームでも使えるんじゃない?」
そんなふうに、別の現場での経験がつながりはじめる。
気づけば、他部署から相談が舞い込むようになり、
人の輪がどんどん広がっていきました。
その瞬間、「自分の仕事が組織の中で意味を持ち始めた」と実感したんです。
「今いる場所」を磨けば、未来は開ける
カル・ニューポートがこの本で伝えているのも、
「環境を変える前に、自分を進化させよう」というメッセージ。
好きなことを探す前に、今の場所でスキルを磨く。
それが“キャリアの土台”になるのです。
転職も選択肢のひとつ。
でも、「今の職場を、成長の実験場にする」と考えれば、
毎日の仕事がちょっと違って見えてきます。
「今ここ」で磨いた力は、どんな環境でも通用する。
そう思えるだけで、仕事の意味がぐっと深まります。
思考の幅を広げる一冊として、『地政学は最強の教養である』もおすすめです。
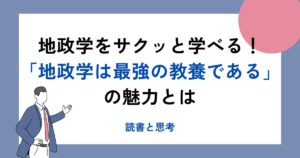
カル・ニューポートが語る「キャリア資本」の考え方
「情熱」よりも「能力」が先にくる
「好きなことを仕事にしよう」という言葉、よく聞きますよね。
でも、カル・ニューポートはそれに真っ向から反論します。
彼が言うのは、「情熱は結果であって、スタートではない」ということ。
まずはスキルを磨き、価値を生み出せるようになってこそ、
本当の意味で“好きになれる仕事”が生まれる。
最初から理想の仕事を探すより、
今の環境の中で「できることを増やす」方が早い。
この逆転の発想が、『今いる場所で突き抜けろ!』の核心なんです。
キャリア資本とは「どこでも通用する力」
ニューポートは、「キャリア資本」という言葉を使います。
それは、自分の市場価値を高める“スキルの貯金”のようなもの。
- 他の人には真似できない専門性
- 組織に貢献できる信頼や影響力
- そして、自分の仕事をコントロールできる力
これらを時間をかけて積み上げることで、
“どんな場所でも求められる人”になっていく。
つまり、「転職して成功する人」と「転職しても迷う人」の違いは、
このキャリア資本をどれだけ持っているかにあるんです。
突き抜ける人は、「地味な努力」を続けている
キャリア資本は、一朝一夕では育ちません。
小さな挑戦を積み重ね、難しい仕事を引き受ける。
その地味な積み上げの先に、ある日突然“突き抜け”が起こる。
ニューポートは、「地味な努力が自由を生む」と言います。
スキルが増えると、仕事の選択肢が広がり、
自分で働き方を選べるようになるからです。
私自身も、異なる部署で積んできた経験が、
結果的に「横断的に動ける人材」としての価値につながりました。
当時はただ必死にやっていただけ。でも、
振り返ればそれが“キャリア資本の蓄積”だったんだと感じます。
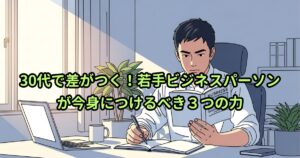
私が“突き抜けた”と感じた瞬間
「信頼できる人」として相談が増えたとき
ある時期から、社内で少しずつ変化がありました。
他部署だけでなく、自分の部署のメンバーからも
「ちょっと相談していい?」と声をかけられるようになったんです。
最初は小さな質問や確認程度。
でも、次第に「一緒に考えてほしい」「意見を聞かせて」と
頼られる場面が増えていきました。
気がつけば、誰かの判断や企画の前に
「とりあえず彼に聞いてみよう」という流れができていた。
これは、スキルだけでなく“信頼”が積み重なった証拠でした。
周りの人が安心して話しかけてくれるというのは、
目立たないようで実はすごいこと。
信頼される人になると、自然と情報が集まり、
自分の視野もどんどん広がっていきます。
そしてその瞬間、
「自分の存在が、チームの中で意味を持ち始めた」と実感できたんです。
スキルが信頼を呼び、信頼がスキルを育てる
面白いことに、相談が増えるほど、
自分のスキルもどんどん磨かれていくんです。
「なるほど、こういう課題があるのか」
「じゃあ、こっちの手法も試してみよう」
人の課題を一緒に考えることで、
自分の引き出しが広がっていく。
スキルが信頼を呼び、信頼がさらにスキルを育てる。
この“好循環”が回り始めると、
仕事が一気に楽しくなります。
どんな場所でも“学びの場”になる
カル・ニューポートは「一流は、環境を選ばない」と言っています。
大切なのは、与えられた場所を“磨く場”に変えること。
私も、異動のたびに最初は不安でいっぱいでした。
でも、「ここで何を学べるか?」と視点を変えるだけで、
環境そのものが刺激的な学びの場に変わっていく。
気がつけば、以前の経験と今の仕事が自然につながり、
社内でも横断的に動けるようになっていました。
このとき初めて、「どこにいても成長できる」手応えを感じたんです。
職場で行動を変えるヒントについては、村田聡一郎氏の著書紹介記事もおすすめです。

誰でも“突き抜け”を起こせる3つのステップ
① 今の職場を「修行の場」として捉える
どんな仕事にも、学びのタネはあります。
「つまらない」「単調だ」と思う作業でも、
見方を変えれば“スキルを磨くチャンス”になるんです。
カル・ニューポートはこういう主張をしています。
「退屈な仕事でも、意図的にスキルを鍛えれば、
それがキャリア資本になる」
私も、最初は慣れない部署で苦戦しました。
でも、「ここで何を学べるか?」という目で見るようにしたら、
一つひとつの仕事が“修行”に変わりました。
その意識の違いが、結果的に成長スピードを大きく変えたと思います。
② 難しい仕事を自ら取りにいく
突き抜ける人は、チャンスを待たない。
「誰もやりたがらない仕事」にこそ、成長の伸びしろがあります。
私も、最初は“ややこしい案件担当”が多くて苦笑いしていました。
でも、その分だけ他では得られない経験が積めた。
問題を一つ解決するたびに、次の相談が舞い込み、
気づけば「頼られる側」に立っていたんです。
人より少しだけ多く挑戦する。
それを続けるだけで、仕事の見え方がガラリと変わります。
③ スキルを“見える化”して発信する
せっかく身につけたスキルも、
誰にも伝わらなければ評価されません。
小さな成果でも、周りに共有することが大切です。
「この改善で工数を30%減らしました」
「新しい方法でお客様の満足度が上がりました」
そんな一言の報告が、信頼を育てるきっかけになります。
自分の強みを“見える化”することで、
社内のネットワークも自然と広がっていく。
それが次の成長につながる“循環”を生み出すんです。
「今の場所で突き抜ける」というのは、
特別な才能が必要なわけではありません。
日々の中で、ほんの少し視点を変えるだけ。
その積み重ねが、いつか“どこにいても通用する自分”をつくってくれます。
成長を支える日々の習慣づくりについては、こちらの「良い習慣リスト」も参考になります。

まとめ:スキル資本を育てれば、どこにいても自由になれる
「今の仕事に飽きた」「自分の成長が止まった気がする」──
そんな時こそ、環境を変える前に“自分の中を整える”チャンスです。
カル・ニューポートはこういう主張をしています。
「自分のキャリアを変える最も確実な方法は、
価値を生み出すスキルを身につけることだ。」
転職も一つの選択肢。
でも、“どこに行っても通用する力”を持っていれば、
あなたは環境に振り回されることなく、自由に働き方を選べます。
私自身、異なる3つの部門を経験してきて感じたのは、
結局、どの環境にも「磨く余地」はあるということ。
最初は違和感があっても、
その場で突き抜ける努力をすれば、必ず道は開けていきます。
「今の仕事をどう活かすか」
「ここで何を学べるか」
──この2つの問いを持つだけで、日常の景色は変わります。
環境を変える前に、自分を進化させる。
その選択こそ、キャリアを長く楽しく続けるための最良の戦略です。
“今いる場所”を突き抜ける人だけが、
次のステージへの扉を開ける。