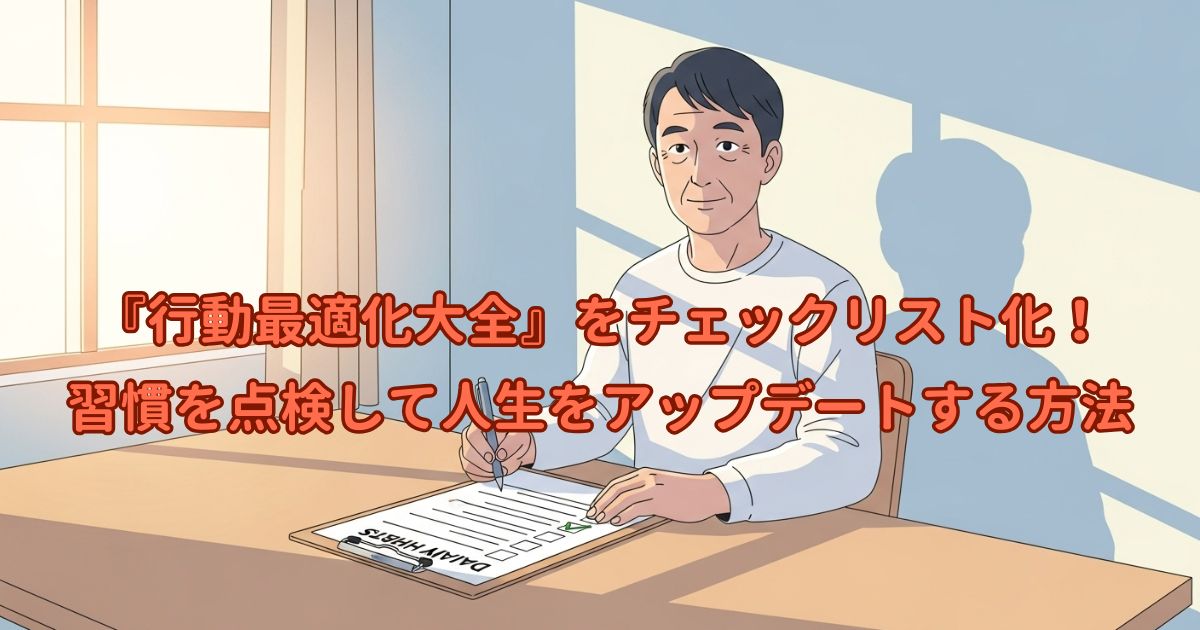朝の時間、どう過ごしていますか?
やる気が出ないとき、どうやって仕事を始めていますか?
楽しんで働けていますか?
樺沢紫苑さんの『行動最適化大全』を読んで気づいたんです。
私が普段やっている習慣の9割が、この本に書いてある!
「行動は感情より先」「まずやってみる」「楽しんだ方がパフォーマンスは上がる」。
どれもすでにやっていたこと。だから本を開くたびに「そうそう!」と納得の連続でした。
この本の良さは、ただ読むだけじゃないこと。
自分の習慣を点検できるチェックシートとして使えるんです。
さて、あなたはどうでしょう?
毎日の行動、最適化できていますか?
『行動最適化大全』とはどんな本か
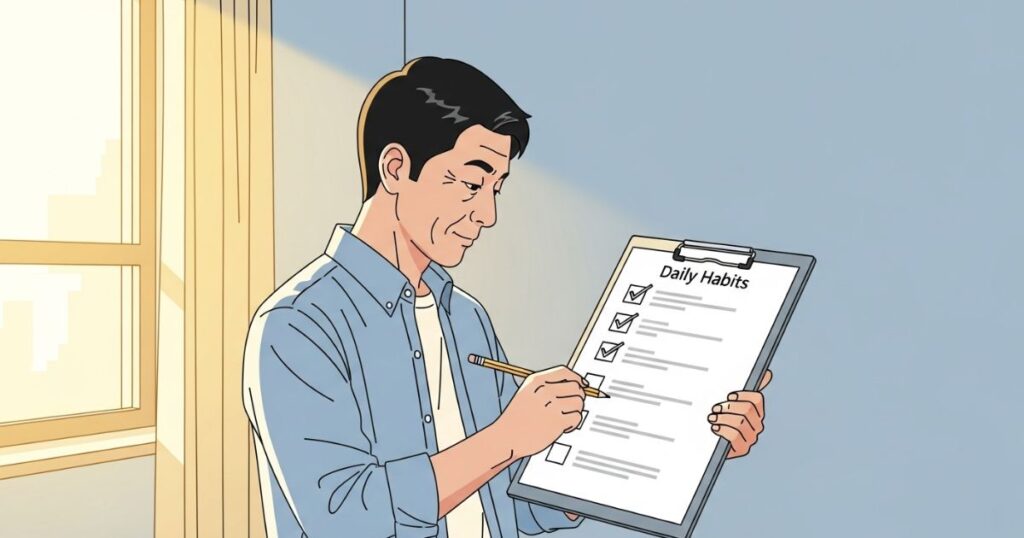
毎日をもっとスムーズに、もっと楽しくしたい。
そう思ったことはありませんか?
『行動最適化大全』は、そんな願いを叶えるための“行動の辞典”です。
著者は精神科医の樺沢紫苑さん。脳科学や心理学の知見をもとに、「どうすれば人生を快適に過ごせるのか?」を徹底的に研究してきた人です。
この本がユニークなのは、ただの知識紹介で終わらないこと。
朝の時間の使い方から、仕事の始め方、学び方、コミュニケーション、健康管理、夜の過ごし方まで。
私たちが毎日必ず直面する“行動のすべて”をカバーしています。
そして、その一つひとつが「すぐに実践できる工夫」として提示されているのがポイント。
「朝は脳のゴールデンタイムだから、集中仕事は午前に」
「やる気を待つのではなく、小さな行動からスタート」
「楽しむ工夫を入れることで、脳はもっと働く」
どれも難しいことではなく、「明日から取り入れられる習慣」です。
さらに、この本の魅力は“チェックシート感覚”で読めること。
ページをめくりながら「これはできている」「ここはまだ弱い」と自己点検できる。
つまり、読むだけで自分の行動習慣が見える化されるんです。
私自身も読んでみて驚きました。
「これ、もうやってる!」と思うことが山ほど出てきて、結果的に9割は実践済み。
逆に「ここは改善の余地がある」と気づく部分もあり、日常をアップデートするきっかけになりました。
要するに、『行動最適化大全』は単なる自己啓発本ではありません。
あなたの行動を“点検”し、“改善”し、“磨き続ける”ための道具。
まさに、毎日の生活を最適化するための実践マニュアルなんです。
習慣チェックシートとしての活用法
『行動最適化大全』の一番の強みは、ただ読むだけで終わらないところです。
この本はそのまま「習慣のチェックシート」として機能します。
どういうことか。
ページを開いていくと、朝の過ごし方、仕事の始め方、学びの方法、人とのつながり、夜のリセット…。
毎日直面する行動が、具体的なヒントと一緒に並んでいます。
だから「これはできている」「これはまだ弱い」と、自分の習慣を点検できるんです。
たとえば「朝のゴールデンタイム」。
本では「午前は最も集中力が高い時間だから、思考系の仕事をここで」と書かれています。
私自身も午前は予定を入れず、集中仕事にあてています。
読んでみて「あ、ちゃんと実践できていたんだ」と確認できた瞬間でした。
逆に、まだ改善の余地がある部分も見つかります。
「夜の締めくくりをポジティブにする」とか「感謝を言葉で伝える」など。
できていないと気づけば、それが次の行動改善のヒントになる。
つまり、この本は「習慣の棚卸しツール」なんです。
できていることを確認すれば自信になる。
できていないことを見つければ、改善のきっかけになる。
チェックシート感覚で読み進めることで、自然と行動がアップデートされていきます。
本を読みながら、自分の習慣をひとつずつチェック。
それだけで、あなたの日常は確実に進化していきます。
私が特に重要だと感じた5つの習慣
『行動最適化大全』には、朝から夜まで、仕事から人間関係まで、実に幅広い習慣が紹介されています。
その中で、私が特に「これは外せない」と思った5つを紹介します。
どれもすぐに試せるうえに、効果を実感しやすいものばかりです。
1. 朝のゴールデンタイムを活かす
午前中は、脳が最もクリアで集中力が高まる時間帯。
だからこそ、この時間に「雑務や会議」を入れるのはもったいない。
私は意識的に午前は空けて、集中仕事や思考系のタスクにあてています。
午後に比べて格段に進みが早いし、達成感も大きい。
まさに「ゴールデンタイムをどう使うか」で、その日の成果が決まります。
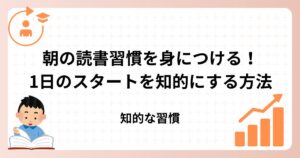
2. 感情より行動を優先する
「やる気が出ないから動けない」ではなく、「動くからやる気が出る」。
本ではそう繰り返し強調されています。
実際、小さな行動をひとつ起こすだけで、不思議とエンジンがかかってくるもの。
私も「感情が整うのを待つ」のをやめて、とにかく手を動かすようにしました。
結果、先延ばしのクセが減り、スタートが速くなりました。
3. 仕事を楽しむ
「楽しい」と感じることは、脳にとって最強の燃料です。
楽しさはドーパミンを分泌し、集中力も記憶力も創造性も引き出してくれる。
私も意識して「遊び心」を仕事に取り入れるようにしています。
たとえば作業をゲーム感覚にしたり、工夫して面白さを見つけたり。
雑談の中で、アイデアを見つけたり。
義務感だけでやるより、圧倒的にパフォーマンスが上がります。
4. アウトプット前提でインプットする
知識を得るだけで終わらせない。
学んだことは必ずアウトプットする。
これは本書の大きな柱のひとつです。
私も本を読んだらブログに書いたり、人に話したり、SNSで発信したり。
アウトプットを前提にすることで理解が深まり、知識が定着します。
「まずやってみる」姿勢が、新しい成長の扉を開くんです。
5. 幸福の三要素をバランスよく満たす
樺沢さんは「幸福」を3つの要素で説明しています。
- セロトニン=運動や生活リズムで得られる安定感。
- オキシトシン=人とのつながりで得られる安心感。
- ドーパミン=目標達成で得られる充実感。
この3つをバランスよく満たすことが、持続する幸福の鍵です。
私自身も「運動」「人との関わり」「目標への挑戦」を意識して取り入れています。
すると、不思議なほど日常の満足感が高まるんです。
この5つは、どれも特別な準備や大きな努力を必要としません。
けれど、日々の積み重ねで人生を大きく変える力を持っています。
だからこそ私は、この本の中でも特に大事にしている習慣として取り上げました。

チェックシート活用で得られるメリット
『行動最適化大全』の良さは、ただ読むだけで終わらないこと。
ページをめくりながら「これはできている」「ここはまだ弱い」と、自分の行動を点検できるんです。
まさにチェックシートのように。
1. できている習慣を確認できる
「朝のゴールデンタイムを活かす」「感情より行動を先にする」など。
本を読みながら「これ、もうやっている」と思えたとき、自信につながります。
私も読んでみて、9割は実践済みだと気づきました。
「今の習慣は間違っていなかった」と確信できることは、大きな励みになります。
2. 改善点がはっきり見える
一方で「ここはまだ弱い」と感じる部分もあります。
たとえば「夜をポジティブに締めくくる習慣」。
本を読むまであまり意識していませんでしたが、「これを取り入れれば、もっと日常が整う」と気づけました。
改善点が明確になるからこそ、効率よく習慣を見直せるんです。
3. 思わぬ気づきが得られる
点検していく中で、行動だけでなく心の持ち方にも発見があります。
たとえば 対人関係。
「1割は嫌い、2割は好き、残り7割はどちらでもない」という考え方が紹介されていました。
振り返れば、確かに今までの人生経験でもそうだったなと納得。
「全員に好かれる必要はない」と思えた瞬間、肩の力が抜けて、人間関係がぐっと楽になったんです。
こうした“心が軽くなる副産物”も、この本の大きな魅力です。
4. 小さな成功体験を積み重ねられる
チェックシート的に「できた/できていない」を確認するだけで、昨日より今日が少し前進した感覚が生まれます。
その小さな成功体験の積み重ねが、モチベーションを自然に支えてくれるんです。
5. 日常全体のパフォーマンスが底上げされる
習慣を整えると、不思議と仕事も人間関係もスムーズになります。
小さな改善が積み重なることで、1日の質そのものが変わっていく。
それが結果として、人生全体のパフォーマンスを引き上げるんです。
つまり、この本は「読む」だけの本ではなく「使う」本。
チェックシートとして活用すれば、できていることは自信に、足りないことは改善のきっかけに変わります。
そして思わぬ気づきが、行動だけでなく心まで最適化してくれる。
そんな実用度MAXの一冊です。
まとめ|一歩を踏み出すために
『行動最適化大全』は、知識を増やす本ではありません。
行動を点検し、改善し、毎日を進化させるための“習慣チェックリスト”です。
私自身、読んでみて驚きました。
気づけば9割はすでに実践済み。
でも「まだ伸ばせる部分」が見つかったことで、さらに習慣を磨き続けられるようになりました。
大切なのは、完璧を目指すことではありません。
ひとつでも「これをやってみよう」と思ったら、まず行動に移すこと。
それだけで、毎日は確実に変わり始めます。
今日からできることは何でしょう?
朝の時間の使い方を見直す?
小さなアウトプットを試す?
それとも、感謝の言葉をひとつ増やしてみる?
あなたが選んだその一歩が、未来をぐっと最適化していきます。
ぜひ、自分の習慣を点検してみてください。
もっと習慣を整えたい方へ。こちらの記事もおすすめです。