ChatGPTを触ってみたけど「うまく答えが返ってこない…」と思ったこと、ありませんか?
実はコツを押さえれば誰でもAIを相棒にできます。
その鍵が「プロンプトエンジニアリング」。
今回紹介するのは、本郷喜千さんの著書『ChatGPTはじめてのプロンプトエンジニアリング』。
本にある基本を自分で試し、ブレストや自己分析、動画作成まで応用してみました。
この記事では「5つのコツ+実践例」をまとめて紹介します。
本書の概要|『ChatGPTはじめてのプロンプトエンジニアリング』とは?

本郷喜千さんの『ChatGPTはじめてのプロンプトエンジニアリング』は、ChatGPTをもっと上手に使いたい人のための入門書。
ポイントは「難しい専門知識はいらない」ということ。
AIに投げかける言葉(=プロンプト)の工夫次第で、答えの質が大きく変わる。
その具体例を、初心者でも実践しやすい形で紹介してくれます。
この記事では、本書のエッセンスを踏まえながら「5つのコツ」をまとめ、さらに私自身が実際に試した事例(ブレストや自己分析など)も交えて紹介します。
読んだその日から「使えるヒント」が見つかるはずです。
プロンプトを磨く5つのコツ【初心者でも実践できる】
ChatGPTをうまく使える人と、なんだかうまく引き出せない人。この差ってどこから生まれるのか?
答えはシンプル。
プロンプト(入力文)の書き方にあるんです。
「難しそう…」と思うかもしれませんが、実はコツさえ押さえれば誰でもすぐに使いこなせるようになります。
ここでは、本書で紹介されているエッセンスをベースに、私自身の体験を混ぜて「5つのコツ」を紹介します。
① 具体的に指示する
ざっくりした質問だと、ざっくりした答えしか返ってきません。
「ビジネスのアイデアを考えて」よりも「40代サラリーマン向け、副業として始めやすいオンラインサービスのアイデアを5つ」と言うだけで、ぐっと精度が上がります。
自分の頭の中を、そのまま紙に書き出すようなイメージで入力するのがコツです。
② 役割を与える
「あなたはプロの編集者です」「あなたは経営コンサルタントです」と役割を設定すると、答えの切り口が変わります。
まるで専門家に相談しているような感覚。
私はブレストをする時に「アイデアに厳しい評論家」と設定したら、刺さる指摘がバンバン出てきました。
役割を与えるだけで、AIの視点は大きく変わります。
③ 背景を伝える
なぜその質問をしているのか?
どんな状況で使いたいのか?
背景を伝えると、答えは一気に現実的になります。
たとえば「ブログのネタを考えて」と言う時に、「40代のビジネスパーソンを励ますような記事を書きたい」と伝えると、ターゲットに合った提案が出てくる。
AIは背景を理解してこそ、本領を発揮します。
少しでも多く情報を提供することにより、回答の精度も上がります
④ 制約条件を入れる
「文字数は600字以内」「箇条書きで」「専門用語は使わない」など、条件を加えると、ぐっと実用的な答えになります。
私はミッションステートメントを作るときに「短く、覚えやすく、毎日唱えられる文に」と伝えたら、心にスッと入る文章が返ってきました。
条件を出すのは、まさにオーダーメイドの指示です。
⑤ 出力形式を指示する
「表でまとめて」「箇条書きで」「ステップごとに」と形式を指定すると、そのまま使える完成度に。
私がトレンド分析をお願いした時は「表形式で、キーワード・検索ボリューム・注目度を整理して」と頼んだら、即ブログに貼れるようなデータが返ってきました。
形式を決めるだけで、作業効率が爆上がりします。
この5つを組み合わせれば、プロンプトの精度は劇的にアップします。
大事なのは「一度で完璧を狙わない」こと。
出てきた答えを見ながら「もっと具体的に」「別の角度で」と投げ直す。
これを繰り返すうちに、自分だけのプロンプトの型ができていくんです。
👉 つまり、プロンプトは「知識」じゃなく「実践」で磨かれるスキル。
今日からさっそく、自分のやりたいことに合わせて5つのコツを試してみましょう!

実践してみた!ChatGPT活用例5選
「プロンプトのコツ」は読んだだけじゃ身につきません。
実際に試すことで「なるほど!」と体感できます。
ここでは、本を参考にして私がやってみた活用例を紹介します。
ブレーンストーミングでアイデア出し
参加者をランダムに3名設定します。
テーマは「知的な生活ってなんだろう」
「自由にアイデアを出して」と頼んでみると、自分では思いつかない切り口がズラッと出てきます。
そこからさらに深掘りすると、面白いアイデアで一杯に。

自己分析で強みを発見
あらかじめ作っておいた「自分史」を読み込ませ、自己分析を依頼。
・私の強み・弱み
・私の大切にしてきた価値観など
自分では思いつかないような切り口で回答してくれます。
第3者からフィードバックをもらっている感覚が本当にあるんですよ。

ミッションステートメントの作成
さらに自己分析結果からミッションステートメントの作成も試しました。
「自分史+ドラッカーの質問をもとに、人生の軸をまとめて」と頼むと、考えが言語化されて驚きます。
AIに背中を押される感覚です。

トレンド分析でブログネタを発掘
「最近のAI関連で注目されているテーマを3つ、理由も添えて」とお願いすると、ざっくりしたニュース記事よりも整理された答えが。
そこから深掘りしてブログ記事のネタにも育てられますよね。
Soraで動画作成に挑戦
遊び感覚ではSoraでの動画作成にも挑戦。
「富士山の頂上でスケッチするシーンを」とプロンプトを投げたら、本当に動画が完成。
自分の頭の中のイメージが形になる体験は刺激的でした。

👉 ポイントは「本に記載されているプロンプトを自分ごとに置き換えて実践すること」。
1回で完璧な答えを狙わなくても、少しずつ改良していけば自然にプロンプト力は鍛えられていきます。
まとめ|プロンプトは「やってみる」が最強の学び
本郷喜千さんの『ChatGPTはじめてのプロンプトエンジニアリング』を読んで強く感じたのは、「プロンプトは知識じゃなくてスキル」だということ。
つまり、知っているだけでは意味がなくて、実際に手を動かしてこそ身につくんです。
今回紹介した活用例——ブレスト、自己分析、ミッション作成、動画生成、トレンド分析。
本に書いてあるプロンプトを 自分の事例で実践することで、新しい発見がありました。
大事なのは「実際にやってみること」です。
このサイクルを回すことで、自分なりの型が自然とできてきます。
さらに、著者が提案している
- 具体的に書く
- 役割を与える
- 背景を伝える
- 制約を入れる
- 出力形式を指示する
という5つのコツ。
これを意識するだけで精度はぐんと上がります。
AIに頼ることは、怠けることじゃなく「自分の考えを整理し、次の行動につなげるための道具」として活用すること。
だからこそ、読みっぱなしじゃなく、日常の中でプロンプトをどんどん試してみることが、自己成長の近道になるんです。
👉 本を閉じたら、そのままChatGPTを開いてみてください。
小さな一歩で、思いがけない成果や気づきが得られるはずです。


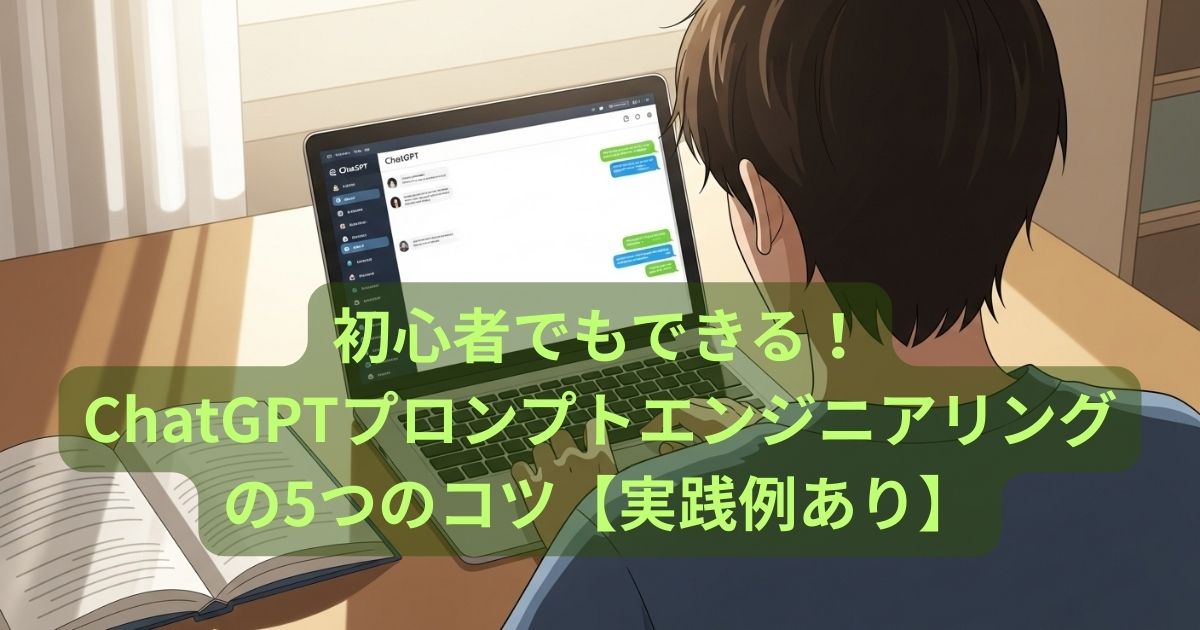
コメント
コメント一覧 (2件)
[…] あわせて読みたい 初心者でもできる!ChatGPTプロンプトエンジニアリングの5つのコツ【実践例あり】 ChatGPTを触ってみたけど「うまく答えが返ってこない…」と思ったこと、ありま […]
[…] あわせて読みたい 初心者でもできる!ChatGPTプロンプトエンジニアリングの5つのコツ【実践例あり】 ChatGPTを触ってみたけど「うまく答えが返ってこない…」と思ったこと、ありま […]