「考える力を高める方法、知りたくないですか?」
日常生活や仕事の中で、「もっと効率的に考えられたらいいのに」と感じたことはありませんか?
問題解決やアイデア出し、意志決定をする際、じょうずに考える力は、今やどんな場面でも必要不可欠です。
『思考の教室』戸田山和久(著)は、まさにその「考える力」を鍛えるための指南書です。
今回は、あなたが日々直面している課題を乗り越えるための、具体的な思考法や実践法を一緒に深掘りしていきます。
あなたも、考える力を高める方法を学んで、より充実した思考生活を送りませんか?
じょうずに考えるとは:論理的思考の紹介
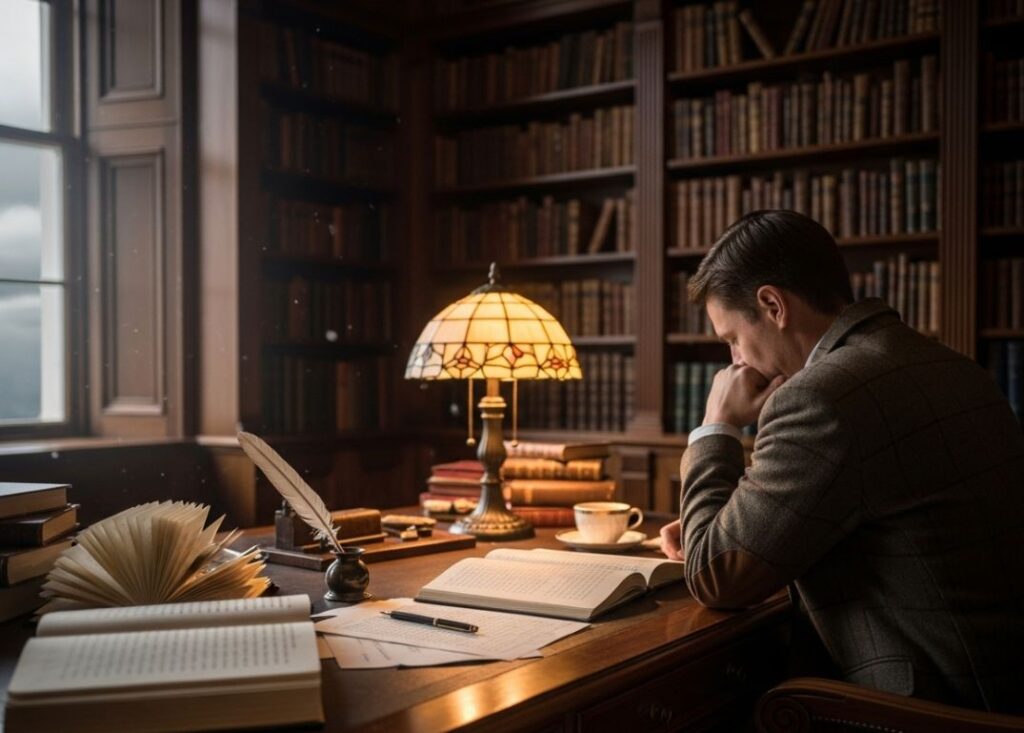
私たちが日々行っている「考える」という行為。
これがいったい何を意味するのか、深く考えたことがありますか?
単に直感的に判断を下しているだけでは、問題解決に至らないことが多いはずです。
考えるとは、ただ思いつきで行動するのではなく、情報を収集し、分析し、筋道を立てて結論を導く過程です。
では、論理的に考えるために必要な要素とは何なのでしょうか?
著者の言葉と解説
『思考の教室』では、「考えること」をどう捉えるか、そしてその方法について解説しています。
戸田山和久さんは、
と述べています。
そして、「じょうずに考える」を「論理的思考」に切り替えて
と述べています。
要は、論理的な思考は以下の構成っていうことですね。
- 自分の主張
- 根拠1
- 根拠2
- 根拠3
そして、根拠は強いサポートになるものが必要ということです。
確かに、ビジネスの世界では必須の思考法ですよね。
ウダウダ説明していたら「ダメなやつ」のレッテルを貼られてしまいます。
そして、根拠が弱ければ、あっさり却下ですよね。
実践的アプローチ
論理的思考を身につけるためには、まず「主張」を明確にし、それをサポートする材料を集めることが大切です。
以下のアプローチを試してみましょう。
- 主張を明確にする: まず最初に、自分が考えている「結論」をはっきりと述べましょう。それが思考の出発点となります。
- サポートを集める: 主張に対する証拠やデータ、過去の経験を集めて、自分の主張を裏付けるサポートを作成します。この「サポート」がなければ、主張が説得力を持たないからです。
- 反論を考慮する: 自分の主張に反対する意見を想定し、それに対してどのように反論できるかを考えることも大切です。これにより、思考がより深くなり、論理的な思考が強化されます。
じょうずに考えるための実践アプローチ
「じょうずに考える」とは、単に頭を使うことではありません。
効果的に考えるためには、どんな方法を取り入れるべきでしょうか?
戸田山和久さんは、以下の3つの手段を紹介しています。
- テクノジーを使って考える
- みんなで/他者と一緒に考える
- 考えるための制度を作って考える
今回は、2つ紹介したいと思います。
実践アプローチ1:テクノジーを使って考える
戸田山和久さんは、「現代における思考は、テクノロジーを活用することが大切だ」と述べています。
そして、テクノロジーとして
と述べています。
実際に、買い物リストや数学の証明などを例にして、根拠を示しています。
根拠の部分は、「なるほど!」という強いサポートになっていますので、実際に本で読んでみてください。
確かに「紙とペン」を使ってアイデアを整理する方法は、デジタルツールでは得られない感覚を得られます。
手で書き出すことで、視覚的に思考が整理され、アイデアがクリアに浮かび上がることがありますよね。
私も在職中は、「紙とペン」を使ってアイデア出しをしていました。
なお、この本は2020年に出版されています。
進化した生成AIが出てくる前に書かれています。
実践的アドバイス:
- ノートを買いましょう: まずは、自分用のノートを買うことが始まりです。
- 「紙とペン」を使って考える: デジタルツールに頼りすぎず、紙にアイデアを書き出してみましょう。そして余白を埋めていきましょう。思考を可視化することです。
実践アプローチ2:みんなで/他者と一緒に考える
思考は一人だけで行うものではなく、他者とのディスカッションや共同作業を通じて広がります。
戸田山和久さんも、「他者との対話を通じて視点が広がり、より深い理解が得られる」と述べています。
そして、そのための重要な要素として 以下3つを紹介しています。
- 自分の考えを伝える:文書設計術
- 相手を考えを学ぶ:クリティカル・リーディング
- みんなで一緒に考える:議論術
文書設計術
戸田山和久さんの「文章を設計する。だから、仕様書を作る」という考えに基づいて述べられています。
そして、サポ文という言葉を使って文章の書き方を説明しています。
要は、先ほど示した基本パターン
- 自分の主張
- 根拠1
- 根拠2
- 根拠3
をもとに、良いサポ文を作成するための方法が示されています。
具体的な方法については、実際に本を読んでみてください。
練習問題もいっぱいあるので、実際にやってみることをオススメします。
クリティカル・リーディング
クリティカル・リーディングを簡単に説明すると、相手の文章を以下の基本パターンに戻すこと
- 相手の主張
- 根拠1
- 根拠2
- 根拠3
そして、相手の根拠にツッコミを考えることで議論のネタを探すことです。
具体的なクリティカル・リーディングの方法については、実際に本を読んでみてください。
具体事例や練習問題もいっぱいあるので、実際にやってみることをオススメします。
確かに、「文書設計術」や「クリティカル・リーディング」を実践することで、論点を効率的に整理できますよね。
お互いの考えが分かれば、生産的な議論を通じて「より良い案」にすることができます。
実践的アドバイス:
- 文書設計術を活用する: 会議やプレゼンテーションで、自分の考えを効果的に整理し伝えるために、文書設計を積極的に活用しましょう。
- 相手の主張をクリティカル・リーディングする:定期的にチームでディスカッションを行い、異なる視点を取り入れましょう。自分の考えだけでなく、他者の意見を聞くことで、問題解決に新たな視点を加えることができます。
議論術
戸田山和久さんは、議論を以下のように示しています。
そのためには、以下が重要と述べています。
実践的アドバイス:
- 自分から議論の場を作ろう:意見の異なる人とディスカッションをしてみよう。他者と協力できる場を多く経験することによって視野を広げることができます。
- 自分が議論の口火を切ろう:まずは反論してもらえるような主張をして、議論を進めてみよう。
まとめ:じょうずに考える力を高めるために
考える力を高めるためには、「テクノロジーの活用」「他者との協力」「考えるための制度作り」といった実践的なアプローチが重要です。
戸田山和久さんが提案する方法を取り入れることで、私たちの思考力は確実に向上します。
まずは、今日からできることを実践してみましょう。
テクノロジーを使いこなし、他者と意見交換をし、日々の生活の中に思考の時間を組み込んでいくことで「じょうずに考える力」が育成されるでしょう。
それと、実際に『思考の教室』戸田山和久(著)を読んでみてください。
論理的な文章で読みやすく、実例も多くあり練習問題もたくさんあります。
分厚い本ですが、絶対に役立つ書籍です。
さて、今回は「考える力」について紹介しましたが、その中で「紙とペンによるアイデア出し」について取り上げました。
以下の記事では「紙とペンによるアイデア出し」について、より詳細に紹介していますので、ぜひこちらの記事も併せて読んでみてください。
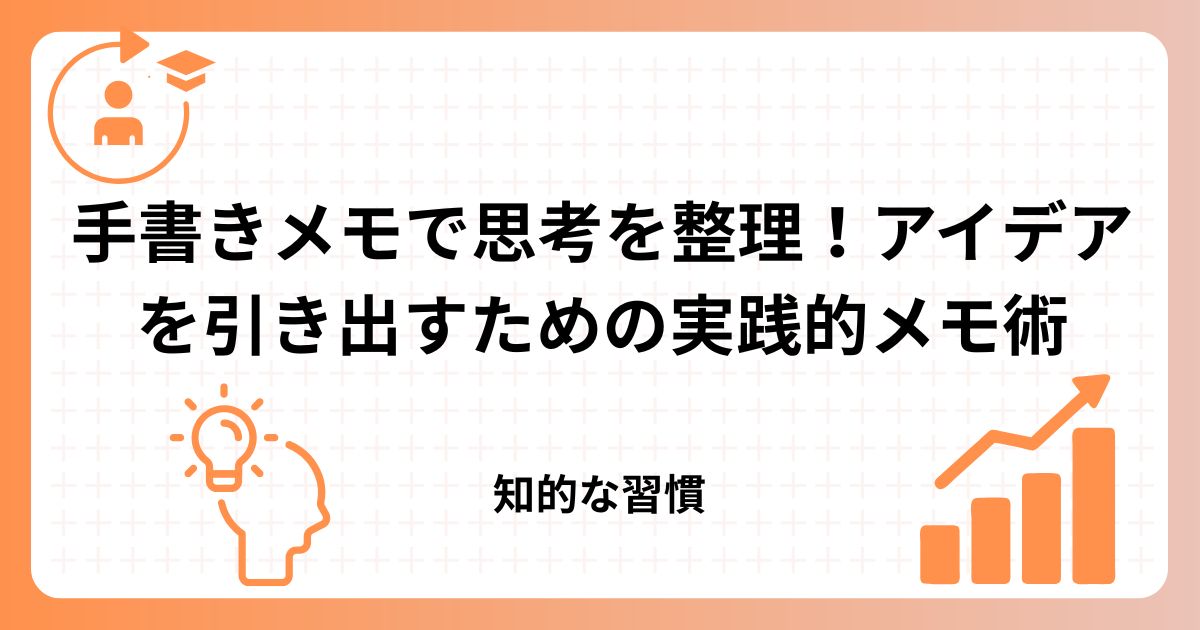

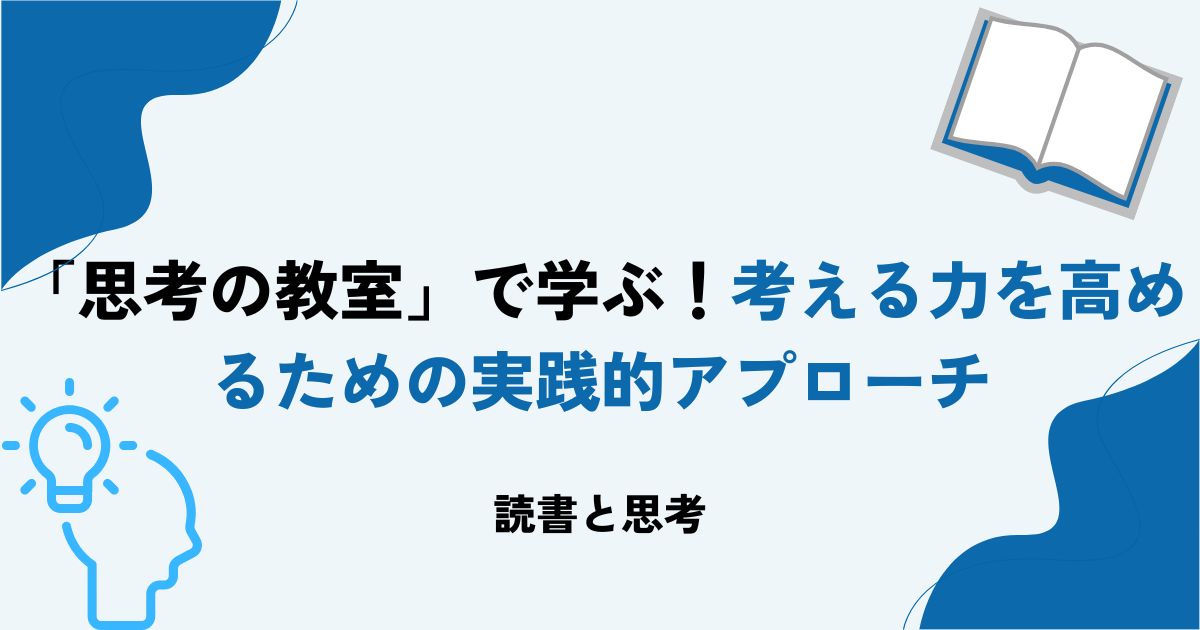
コメント
コメント一覧 (5件)
[…] あわせて読みたい 「思考の教室」で学ぶ!考える力を高めるための実践的アプローチ 「考える力を高める方法、知りたくないですか?」 日常生活や仕事の中で、「もっと効率的に […]
[…] あわせて読みたい 「思考の教室」で学ぶ!考える力を高めるための実践的アプローチ 「考える力を高める方法、知りたくないですか?」 日常生活や仕事の中で、「もっと効率的に […]
[…] あわせて読みたい 「思考の教室」で学ぶ!考える力を高めるための実践的アプローチ 「考える力を高める方法、知りたくないですか?」 日常生活や仕事の中で、「もっと効率的に […]
[…] あわせて読みたい 「思考の教室」で学ぶ!考える力を高めるための実践的アプローチ 「考える力を高める方法、知りたくないですか?」 日常生活や仕事の中で、「もっと効率的に […]
[…] あわせて読みたい 「思考の教室」で学ぶ!考える力を高めるための実践的アプローチ 「考える力を高める方法、知りたくないですか?」 日常生活や仕事の中で、「もっと効率的に […]